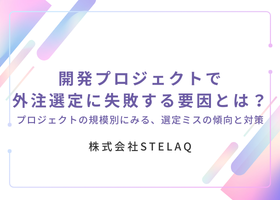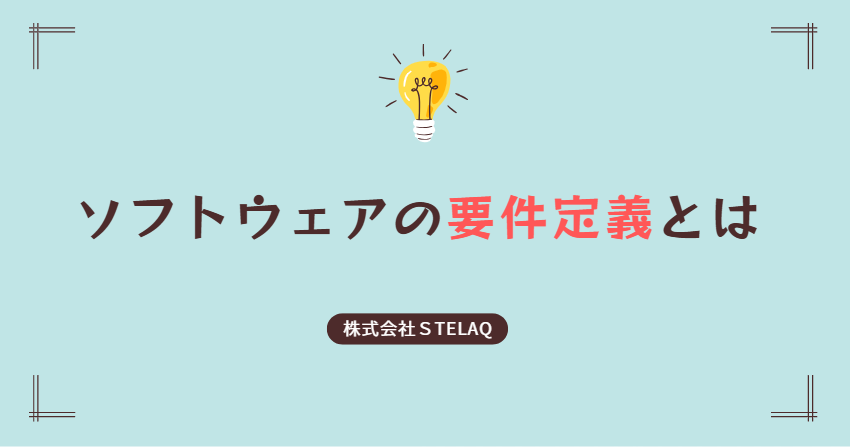
システム開発プロジェクトにおいて「要件定義が不十分で失敗した」という話を聞いたことがある方も多いのではないでしょうか。実際、日経コンピュータの調査では、プロジェクト失敗理由の筆頭が「要件定義の不備」であると報告されています。
ソフトウェア開発を成功させるためには、プロジェクトの土台となる要件定義を正確に行うことが欠かせません。
この記事では、ソフトウェア要件定義の基本概念から具体的な進め方、よくある失敗パターンとその対策まで、実務で役立つ知識を体系的に解説していきます。
ソフトウェア要件定義とは「機能」や「性能」を定義するプロジェクトの上流工程
①ソフトウェアの要件定義とは
ソフトウェア要件定義とは、クライアントの「要望」や「需要」を、具体的な「要件(機能・非機能)」に落とし込み、設計や実装の指針を練る作業です。
システム開発プロジェクトの序盤で「どのようなソフトウェアを作るか」を明確に定めるプロセスであり、プロジェクト全体の土台を形成する、極めて重要な上流工程です。
具体的には、ユーザー(発注者)が望むことや解決したい課題(要求)を正しく把握し、それを実現するために必要な機能や条件(要件)を洗い出していきます。要件定義の成果物である「要件定義書」には、実現すべき機能要件と非機能要件、制約条件などが整理され、プロジェクトの設計図として機能します。
②要件定義はなぜ重要なのか
要件定義により、開発者はユーザーのニーズを漏れなくシステム設計に反映でき、後工程の設計・実装フェーズで「何を作るか」がブレなくなります。要件定義は開発プロジェクトを成功に導く基盤として、極めて重要な役割を果たしていると言えます。
日経コンピュータの調査では、システム開発プロジェクトの失敗理由の筆頭が「要件定義の不備」であったと報告されています。また、要件定義の不備がその後の度重なる仕様変更を招き、結果的にプロジェクト全体の失敗につながってしまうケースが後を絶たないといいます。
要件定義でのミスが恐ろしいのは、それが後工程で発覚した際の影響です。要件の見落としや誤りに気付くのが遅れるほど、その修正には莫大な時間とコストがかかります。
ソフトウェア要件定義における「要求」と「要件」の違い
要件定義を正しく進めるためには、まず「要求」と「要件」の違いを理解することが大切です。日本語では紛らわしい両者ですが、意味が明確に異なります。
①要求(要求定義)とは
要求とは「ユーザー(発注者)がシステムに求める条件や機能」のことであり、要するにユーザー側のビジネス上のニーズや希望を整理したものです。発注者であるユーザー企業が「どんなシステムを構築したいか」「そのシステムで何を実現したいか」といった要望を洗い出し整理したものが要求定義になります。
②要件(要件定義)とは
一方、要件とは「その要求を実現するためにシステムが備えるべき具体的な機能・性能・条件」を指し、開発者側が技術的視点でまとめ上げたものです。ユーザーから受け取った要求定義をもとに、開発ベンダーとユーザー双方で認識をすり合わせながら、実現可能な形に要件へ落とし込んでいく作業が要件定義となります。
③両者を区別することの重要性
ユーザーの要求をそのまま要件として開発を始めると、「ユーザーの真のニーズとシステム要件がズレていた」という事態に陥りかねません。
また要求(ビジネス上の目的)が曖昧なまま要件化すると、開発途中で「本当に必要な機能は何か」が定まらず迷走するリスクがあります。
要件定義では、「ユーザーが漠然と抱く要望(要求)」を「後から検証可能な具体条件(要件)」へ正しくブレイクダウンすることが重要です。
「ソフトウェア」と「システム」の要件定義の違い
「要件定義」という言葉にはいくつかレベルがあります。ソフトウェア要件定義とシステム要件定義は混同されがちですが、そのスコープに明確な違いがあります。
①システム要件定義の特徴
システム要件定義は、ハードウェア、ネットワーク、運用体制を含む全体構成を検討する上位の工程です。開発対象システム全体の要件を定義し、システム全体に必要な機能・性能・外部連携・運用体制・ハードウェア構成・ネットワークなど幅広い事項を決定します。
システム全体の「あるべき姿」を描き出す作業と言えるでしょう。例えば新しい業務システムを導入する場合、まずシステム要件定義で「システム全体の機能一覧」「必要な性能(例えば同時ユーザー数や可用性目標)」「システム構成」などを定義します。
②ソフトウェア要件定義の特徴
一方、ソフトウェア要件定義は、システム内のソフトウェア機能や仕様に絞って詳細化する工程です。そのシステム内に組み込まれる一つひとつのソフトウェア(プログラム)ごとに、必要な詳細機能やUI、データ項目などを詰めていく作業です。
③対象とするスコープの違い
システム要件定義とソフトウェア要件定義をレイヤーで分けると、システム要件定義が上位、ソフトウェア要件定義が下位関係にあたると言えるでしょう。
システム開発のプロジェクトでは、まずシステム全体の要件(システム要件定義)が策定され、その中でソフトウェアが担当するべき部分について、より詳細なソフトウェア要件定義が行われるという流れが一般的です。
例えば、システム要件定義の中で「営業情報共有機能」や「在庫管理機能」といったソフトウェア単位の機能が出てきたら、それぞれの画面項目や処理ロジック、データベース仕様などをソフトウェア要件定義で詳細化します。このように対象スコープが異なることを理解し、プロジェクト規模に応じて適切に使い分ける必要があります。
ソフトウェア要件定義の基本的な進め方 7ステップ
要件定義の基本的な流れは以下の通りです。
| ステップ | 概要 |
|---|---|
| 1.開発目標の明確化 | システムの導入目的や現状の課題を経営層・依頼部門と確認し、「なぜ開発するのか」「誰が使うか」を明確化。 |
| 2.ユーザー要求のヒアリング | 要求を一覧化し、5W2Hで具体化。本当の目的や課題を引き出す。曖昧な要求はグルーピング・整理。 |
| 3.機能要件の洗い出しと優先順位付け | Must/Want分類で重要度を設定。優先度に基づき対応範囲を明確化し、スコープの膨張を防止。 |
| 4.非機能要件の明確化 | 性能、可用性、信頼性、保守性、セキュリティ、互換性など。定量的な定義とユーザーへの積極的なヒアリングが必要。 |
| 5.制約・前提条件の整理 | 技術・予算・スケジュール・法規制などの制約を明文化。後工程でのトラブルを防ぐ。 |
| 6.要件定義書の作成・レビュー | 機能/非機能要件を文書化し、表現の一貫性・用語の揺れ・矛盾をチェック。認識のズレを防止。 |
| 7.合意形成 | 要件定義書をユーザーと共同レビュー。運用担当者も交えて妥当性を確認し、双方で合意・サイン。設計へ進行。 |
非機能要件の定義を成功させるコツ3選
非機能要件の定義を成功させるポイントを3つに分けて紹介します。
1. 指標(RASIS+α)を活用し、品質面を漏れなく定義する
2. シナリオベースで「誰が・どんな状況で・どれくらい」かを明確にする
3. テストの観点を要件定義時に組み込む
非機能要件は、システムが提供する機能「以外」の要件、つまりシステムの品質・性能・運用性などに関する要件です。ユーザーにとっては裏方の条件であるため見落とされがちですが、非機能要件を疎かにするとシステム稼働後に重大なトラブルを招くことがあります。
1. 指標(RASIS+α)を活用し、品質面を漏れなく定義する
非機能要件を網羅的に検討するために、品質特性の指標を活用します。例えばRASISは信頼性・可用性・保守性・安全性の頭文字を取った指標で、コンピュータシステムのサービス品質を評価する代表的な枠組みです。
- Reliability(信頼性): 故障や障害への耐性(障害発生率などで評価)
- Availability(可用性): システム継続稼働性(稼働率や復旧時間で評価)
- Serviceability(保守性): 障害時の保守容易性(修復のしやすさ、メンテナンス性)
- Integrity(完全性): データの一貫性・保全性(障害時にデータが壊れないこと)
- Security(機密性): 情報資産の安全性(不正アクセス防止や機密保持)
RASIS(信頼性・可用性・保守性・安全性)に加えて、拡張性やユーザビリティも対象とすると良いでしょう。
2. シナリオベースで「誰が・どんな状況で・どれくらい」かを明確にする
非機能要件は「高速に動作してほしい」「安全にしてほしい」など抽象的に語られがちです。しかし抽象的なままでは人によって解釈が異なり、後から「思っていたのと違う」という齟齬が発生します。
シナリオベースのアプローチとは、実際のシステム利用状況をシナリオとして描き、その中で求められる品質特性を導き出す手法です。例えば「ピーク時に同時アクセスが急増した場合」「大規模障害が起きた場合」などシナリオを設定し、それぞれの場面で必要となる性能・信頼性・復旧手順などを洗い出します。
そして「ピーク時には○件/秒を99%で3秒以内で応答」など状況と数値を組み合わせることで認識のズレを防ぎます。
この際、可能な限り数値で目標を定義しましょう。数値目標があれば、開発段階で性能テストや負荷テストによる検証ができますし、運用後もその指標をモニタリングして達成度を測定できます。
3. テストの観点を要件定義時に組み込む
非機能要件は定義して終わりではなく、テスト計画や運用設計と結び付けてこそ意味があります。非機能テスト(性能・セキュリティ・UXなど)の観点を先に決め、要件→指標→テストケースが紐づくようにします。
要件定義の段階からテスト担当・運用担当とも情報共有し、フィードバックを得ておくと、実現困難な要件やテスト不能な要件に早めに気付けます。
ソフトウェア要件定義でよくある失敗パターン3選と対策

最後に、要件定義で陥りがちな失敗パターンと、その対策をお伝えします。
失敗パターン①曖昧な表現で関係者の認識にズレが生まれる
抽象的な要求のまま要件定義を急ぎ、後になって認識ズレが発覚するケースです。対策は、用語の意味や要求の水準を整備し、レビューで適切な定義に直すことです。
要求段階で徹底的に具体化し、5W2Hで要求を掘り下げ、あいまいな表現は具体的な数値や条件に置き換えます。また本格的な要件定義書を作る前にチーム内で要求分析内容をレビューし、解釈の違いがないか確認します。
失敗パターン②スコープがどんどん広がり要件が肥大化する(スコープクリープ)
顧客からの要望を際限なく盛り込み、システム要件が肥大化して収拾がつかなくなるケースです。こうなると、予算やスケジュールを大幅に逸脱し、品質や納期にも悪影響が及びます。
要求事項のMustとWantを明確に切り分け、必須でない要望は思い切ってスコープ外にする判断が必要です。追加の要望が出た場合は、必ず影響範囲とリソースを再評価し、必要なら要件や納期の調整を早期に行うルールを徹底しましょう。
失敗パターン③開発チームとコミュニケーション不足
要件定義段階から開発者・テスト担当・運用担当との情報共有が不足していると、技術的に実現困難な要件が紛れ込んだり、後工程で予期せぬ問題が発生したりします。
対策は、定例ミーティングの議事録と全要件を共通リポジトリに保管し、情報の共有と透明性を確保することです。要件定義段階から開発者・テスト担当・運用担当とも情報共有し、可能であれば要件に対するフィードバックをもらいます。
例えば「この性能要件を満たすには最新鋭の機器が必要だが予算オーバーでは?」といったリスクは、要件を確定する前に指摘し調整すべき内容でしょう。
まとめ
ソフトウェア要件定義は、ユーザーのニーズを的確に捉え、後工程で検証可能な具体的要件へ落とし込むプロセスです。その出来がプロジェクトの成否を決めると言っても過言ではなく、プロジェクトでもっとも注力すべき工程の一つです。
要件定義の重要性を再認識し、丁寧に進めていきましょう。
STELAQのソフトウェア開発支援サービスでプロジェクトを成功に導きます
STELAQでは、自動車、金融、医療、IoTなど多様な産業での豊富な開発実績を基盤に、貴社のソフトウェア開発プロジェクトを成功へと導きます。体制構築や要件定義含む上流工程のコンサルティングから、開発及び検証まで一気通貫の支援で、プロジェクト全体の課題解決をサポートします。
- 多様な産業・ドメインでの豊富な開発実績
- 上流工程から開発・検証・教育まで一気通貫の支援体制
- 個社に合わせた柔軟なサポートと早期戦力化
ソフトウェア開発プロジェクトの推進、品質向上、人材育成に課題をお持ちでしたら、ぜひ一度STELAQにご相談ください。貴社の状況に合わせた最適な支援プランをご提案し、プロジェクト成功を全力でサポートいたします。